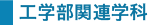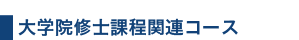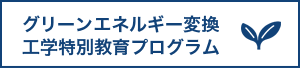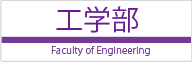当研究室希望学生へ
当研究室では、環境・エネルギー問題の解決に貢献できる未来の単結晶材料に関する研究を行っています。地域活性化・地場産業振興へ貢献する研究、異分野融合につながる研究を目指しています。
環境・エネルギー分野に興味がある方、単結晶について研究してみたい方は、ぜひ研究室を訪ねてみてください。他大学から大学院進学を希望する方も含めて、いつでも大歓迎です。
主な研究テーマについて
浮遊帯溶融法 (FZ 法)、溶媒移動浮遊帯溶融法 (TSFZ 法)、フラックス法などの結晶育成方法を用いて機能性化合物の単結晶を育成する研究を行っています。
特に、環境・エネルギー関連材料に注目して、その単結晶の育成に取り組んでいます。
具体的なテーマは、以下の通りです。
(1) リチウムイオン伝導体の単結晶育成 -次世代の全固体リチウムイオン電池への応用ー
(2) 蛍光体の単結晶育成 -単結晶型 LED 照明への応用ー
(3) 誘電体の単結晶育成 -新規誘電体材料の基礎的研究ー
(4) ナトリウムイオン伝導体の単結晶育成 ーナトリウムイオン電池用材料の開発ー
(5) (酸)窒化物の単結晶育成 -新機能創製ー
上記は一例ですが、研究したい材料があれば、自ら研究テーマを立案することを歓迎します。
ゼミについて
基本的には、学生間で話し合いどんなゼミを行うか決めてもらいます。
これまでの例
月間報告 (全員 月1回 発表10分、質疑応答10分)
論文発表 (全員 月1回 発表20分、質疑応答10分)
・ゼミは全員出席してもらいます。(ただし、面接、他大学入試、体調不良など、やむを得ない事情により欠席する場合は事前に連絡すること)
・先輩・後輩・同期の発表に対して積極的に質問するとお互いに理解が深まります。
研究室の方針
当研究室は、綿打教授・長尾准教授と研究グループを構成してます。研究室の基本方針は綿打・長尾研究室と同じです。
研究の進め方:
最初は、自分の興味関心のあるものを具体的にしぼってみてください。対象をしぼったあとは、その対象に関してこれまでにどんな研究が行われてきたか、どんな問題が解決され、どんな研究成果が挙げられたかを調べることから始まります。当研究室では、”とりあえず実験をやってみる”ことも研究をはじめる一つの選択肢として大事だと思いますが、まずは、類似の研究はないか文献調査を行い、論文をよく読み、”研究の調査をする”ことをお勧めします。ほとんどの論文は英語で書かれています。はじめは英語に慣れておらず読むのに苦労するかもしれません。あせらずにじっくり勉強してそこを乗り越えてほしいと思います。そして、まだ解決されていない問題点などから具体的な研究目的を設定し、それを達成するための研究計画を考えます。その結果、装置の開発もしくは既存装置の改良が必要なるかもしれません。そうしたら装置を立ち上げ、ようやく実験を行います。得られた実験結果についてしっかり考えることが重要です。 そして必要であれば次の実験計画を立てます。(ここでまた文献調査が必要になるかもしれません。”ゼミなどの報告のための実験をしない”よう気を付けましょう。本当に必要な実験・分析なのか調べ考える過程も大事な研究活動です。) こうしてデータを積み重ねていき、学会発表や論文等として研究成果を発表します。
研究室での生活:
学生居室は、他研究室の学生と共通部屋になっており学年や所属コースに関係なく一緒になっています。他研究室の学生同士のコミュニティーにすることで、幅広い知識、価値観を身につけ、研究の視野を広げることにつながります。もちろん、遊んだり騒ぐ場所ではありません。居心地のよい環境を築くために、”ルール”、”マナー”を守り、”他人の視点”を意識して行動してください。共同で使用する物、スペースは使用した後は整理整頓と清掃を心掛け、私物化しないこと。何か問題を感じたら放置せずに、報告・相談してください。
研究生活で学んでほしいこと:
研究に必要な知識や技術はもちろんですが、”自主性”、”積極性”、”協調性”、”プレゼン能力”、”想像力”、”共感力”、”論理的思考力”、”感謝の気持ち” などを身につけてほしいと思います。研究室では、自ら学ぼうとする積極的な姿勢がないと何も得られません。現在の研究環境があるのは、歴代の先輩たちが蓄積してくれたからです。それぞれの代で研究室を運営して (責任範囲を考え、わからないことは相談) 次代に何かを残していってください。失敗が許されるこの時を最大限に活かして学んでください。そうして手に入れた何かが社会に出てからきっと役に立つ能力となることを願います。